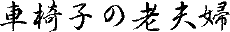
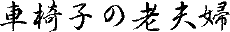
ある夏の夜、下町の小さな地下鉄の駅を上がったところで私は主人の車を待っていた。目の前は浅草橋から浅草に通じる道路で交通量がとても激しかった。日も暮れて夏の暑さもやわらぐほっとする夜だった。私たちは共稼ぎの為、私が会社から帰宅する時間に合わせて主人に車で駅まで迎えに来て貰い、その足で夜遅くまで開いている田原町のスーパーに買い物に行くのが常になっていた。 ぼんやり街の光景を見ていたら目の前の信号が青になり、車椅子を押して初老の老紳士が横断歩道を渡ってきた。車椅子の肘の部分にいくつかの箱が重なって積まれていた。その陰に見えなくなりそうに老婦人が椅子に座っていた。やがて二人は前を通り過ぎて私の視界から消えて行った。
しばらくするとまたその車椅子が私の前を通り過ぎ、別の方向に向かって行った。さっき積まれていたたくさんの箱はすでに無くなっていた。どうしたんだろう。。。
「あっそうかぁ。あそこの先にゴミ置き場があるからきっとあそこに捨てに来たんだ。」とわかった。私はまたその車椅子を目で追っていた。すると今度はポストの前で止まった。そして座っていた老婦人がポストに手紙を入れた。するとまたその車椅子はゆっくり私の前を通り過ぎて青になった横断歩道を渡って行った。何気ない当たり前の光景だが、ほんとうにほのぼのする光景だった。今まで色々なことがあったおふたりだろう。今は奥様が車椅子の生活をされているようだが、身体の動く旦那様がとてもやさしく車椅子を押し、いたわっていらっしゃるご様子。そして、たとえゴミ捨てや郵便出しでもご一緒に来られる様子に本当に心があたたまる思いがした。
私たちもいつか年をとり、どちらかが車椅子の生活になったとしてもお互い助け合い、1日でも長く一緒に暮らして行けたらと深く思った。また、たとえゴミ捨てや郵便出しのような日常生活においても気軽に車椅子でも外出できる福祉環境がこれからはますます必要になってくると考えさせられる情景だった。
駅前には今年も大きな「隅田川花火大会」の交通規制、見学場所の広域地図の掲示板が立てられていた。あのおふたりも車椅子を押しながら花火見物ができる場所があればいいなとふっと思った。
車椅子を見送った後に主人の車が目の前に止まった。
1997年 夏 By Tama-Chan