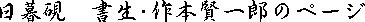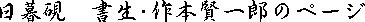第22回 浅草で拾ったメディアの紹介 番外編[97/05/18]

【タイトル】「春、とさねよしいさ子」
高校2年のときである。(高校は元浅草にあった。)国語の授業中であった。そのときの先生は「春のおわりはものがなしい」と述懐した。ほんの刹那なのだが、その瞬間があるという。皆は、来るべき夏に対しての期待感が先行する、とその刹那を否定していた。各々の季節にはその訪れを予感させる期待と去りゆく時の寂しさを持ち合わせているのだが、春にはその寂しさがわからないというのだ。かといってその先生は決して、例えば桜が散りゆくときのあの無常感のような、そんな単純なことを述べているわけではない。
だがまてよ、とあたしは立ち止まってみた。立ち止まってひっかかったまま、何か感ずるところがあるのだけれどそれが何だかはうまく言い表せない。言い表せないで幾年もの春のその刹那を過ぎようとしても未だわからない。それは風なのか、光なのか、草いきれなのか、痛みなのかさえも。
そして今年はそんな時期が来る前のうららかな日、さねよしいさ子のライブを見に行った。彼女は最近、メジャーな活動をしていないというので、大ファンのあたしはそんじゃとおもいえいっとこのライブをみにいったのだ。そしたら彼女もうたっていた。
「春はなぜせつないのかぜが吹くそよそよと春はなぜほほえむのとんでくよふわふわと」
あの時の先生と同じような想いをこの詩人も想っていたのか。そのうたは前からあったうただけど、今日に限ってそのフレーズが釣り針のようにひっかかってしまった。
もしかしたら、あの先生には刹那に感じたその瞬間も、この詩人にとっては春全部そのものなのかもしれないし、あるいはその刹那だけが春そのものなのかもしれない。深いといってしまえばミもフタもないけれど、花鳥風月だけではない春が見え隠れするような、そんな気がする。
そして浅草に限っていえば、(三社祭もちかづいてくるけど)過日は桜の花びらを一面に敷き詰めたあの「春のうららの隅田川」にその鍵が水中深く沈んでいるような、そしてそれは、真夏の夜のあの水際の喧騒に掻き消される前には顕在してくるような、そんな気がする。
|